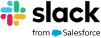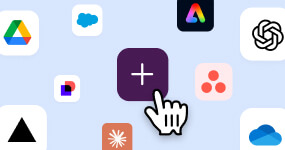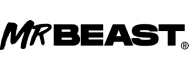株式会社文藝春秋は大正 12 年(1923 年)に作家の菊池寛氏によって創設された、芥川賞や直木賞の幹事も務める日本でも有数の老舗出版社です。『文藝春秋』『週刊文春』『 CREA 』『 Sports Graphic Number 』などの雑誌に加え、単行本、文庫、新書など多くの書籍も手がける同社はまさに「紙文化の会社」。現在の社員数は 344 名ですが、 2019 年夏の時点でその半数を超える 188 名の社員が社内外のコミュニケーションに Slack を活用しています。紙の力が圧倒的に強い同社でここまで Slack が浸透した理由は何だったのでしょうか。
横断コミュニケーション改善のため Slack を導入
「作家が創設した会社ですから、何よりも編集の現場を重んじる文化があります。各編集部の独立性もすごく強い」と話すのは、オール讀物・別冊文藝春秋編集長(当時)の大沼貴之さん。そんな同社に大きな転機が訪れたのは 2017 年のこと。各編集部を横断したコンテンツを扱う WEB メディアが誕生したのです。まずは『 CREA 』と『 CREA Traveller 』のコンテンツを扱う「 CREA WEB 」がスタートし、続いて『週刊文春』の記事を中心に独自コンテンツや、小説や単行本などに関する様々な情報を配信する「文春オンライン」も始まりました。
部署の独立性が強かったところに横断メディアが登場したことで、デジタル部門と編集部、あるいは各編集部間で、これまでにはなかったような細かな調整作業が発生するようになりました。また部署を超えた情報共有が行き届かず、関係者の間で「聞いている/聞いていない」といったトラブルがたびたび生じるようにもなっていました。
実はその当時すでに、社内には無料版の Slack が導入されていて、文春オンラインでも活用しようと動き始めたところでした。しかし実際に使っている人は、まだほんの数名程度。デジタル部門でも、メールや内線電話、あるいは口頭でコミュニケーションが行われていたそうです。デジタル・デザイン部の浪越あらたさんが文藝春秋に入社したのは、まさにそんなタイミングでした。
「電話や口頭でのやりとりは記録に残らないため、あとからその内容を確認したり、振り返ろうとすると、それだけで多くの時間がとられてしまいます。またメールでは関係者を To や CC に加え忘れて、情報が正しく行き渡らないといったことも起こりがちでした」と浪越さんは振り返ります。さらに、編集者の経験や人脈を重視してきたため情報は個々の社員のもとに蓄積されていて、会社の共有財産となっていないことも課題とでした。このような背景から、Slack 活用への思いが強くなってきたといいます。
一方、文芸誌の編集長をしていた大沼さんは、「他部署との情報共有がうまくいかない」「他部署のアイデアが欲しいような案件があっても、うまく呼びかけができない」などの問題を感じていました。加えて、「デジタル+アナログ」で仕事量が増えていたこともあり、状況改善のため Slack を使い始めていたのです。
3 つの工夫で利用メンバーが増加
「文春オンライン」での導入をきっかけに、徐々に文藝春秋の社内で使われるようになった Slack。しかしそれぞれの部署でメンバーがボトムアップのような形で導入を進めたため、当初はワークスペースが乱立する事態となりました。
そこで浪越さんらデジタル部門では 2018 年末~19 年はじめにかけて、ワークスペースの統合に乗り出します。それによって、 25 名ほどだった利用メンバー数は右肩上がりに増加し、メッセージの数も急増。そこでさらに社内にアピールするため、役員に対するプレゼンや、社員向けの説明会を実施しました。これが「役員プレゼンまでした Slack って何だ?」と社員が興味を持っきっかけに。説明会後はさらにメンバーが増えたほか、メッセージ数も 1.6 倍になるなど、大きな効果がありました。
「新しいものを取り入れることに抵抗感の強い人もいるので、あまりぐいぐいとならないように、今はまだゆっくりと導入を進めている段階です」という浪越さん。一方で Slack を始めたメンバーには積極的に活用してもらえるように、自ら率先してやってみせていることが 3 つあるそうです。
1 つ目はぱっと見て内容がわかるような 1 行程度の短いメッセージを頻繁に投稿すること。メールだとある程度情報がまとまらないと送信しづらく、また返信も一言では済ませづらいもの。Slack なら一言、二言を頻繁にやりとりできることを知ってもらうための取り組みです。
2 つ目は画像を投稿すること。これは、 Slack では画像もやりとりの中に直接表示されるため、文脈がわかりやすいということを伝えるためです。
3 つ目は趣味のチャンネルを自由に作れるようにすること。まずは Slack に慣れてもらえるように、気軽にコミュニケーションできる雰囲気を作ったのです。
こうした取り組みの甲斐もあって以降も Slack のメンバー数、やりとりされるメッセージ数とも右肩上がりに増え、冒頭で紹介したように現在では社員の半数以上が使うようになりました。
Slack 活用で時短に成功、業務品質も向上
ワークスペースを統合し本格導入してからまだ 1 年たらずですが、社内からは早くもポジティブな声が多く寄せられているようです。
「メールが Slack に置き換わったことで、検索するだけで情報が出てくるようになり、捜し物の時間が激減したとみんな言っています。またその都度共有したい情報をチャンネルに流すことで、互いの状況を確認するための会議もなくなりました。このことも効率化に大きく寄与しています」(浪越さん)。
ほかにも今まで交流のなかった他部署や、取材のためすれ違いが多かったメンバーとのコミュニケーションが密になることで、新たな企画のアイデアが生まれやすくなったほか、そのアイデアにリアクションを返すことで具現化へのスピードがアップ。また管理職はチャンネルでのやりとりから、ひとりに業務が偏っていないかチェックできるようになり、偏りすぎている場合は誰かがカバーすることで業務品質を高められるようになりました。
さらに個人に蓄積されていた知見がログとして残ることで、会社の資産に。例えば本のプロモーションをするとき、過去に良かった事例を Slack のチャネルの中から探して活用することで、成功事例を横展開しやすくなりました。
「自分の働き方にもデジタル化を進めないと、本当の意味のデジタルシフトは実現できない」
このポジティブな効果をより多くの社員に感じてもらえるよう、これからも Slack を浸透させていきたいという大沼さんと浪越さん。たとえば大沼さんは人事異動をきっかけにした普及にも期待しています。 Slack を使っているメンバーが未導入の部署に異動して、その部署に Slack を広める。そんな風になれば、大沼さん、浪越さんが思い描く、社内のコミュニケーションが Slack だけでできる日も、そう遠くないかもしれません。
「出版社は今、デジタルシフトのまっただ中です。でもただアウトプットをデジタル化するだけじゃ、本当の意味でのデジタルシフトとは言えません。自分の働き方にもデジタル化を進めて、このスピードへ順応できるようにしていかなければいけない。そのために Slack が非常に有用なのではないかと思っています」。