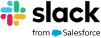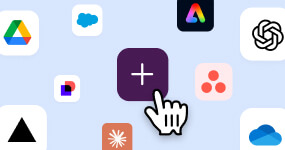少子高齢化が急速に進む日本においては、できる限り少ないリソースで効率的に成果を上げる企業活動が求められています。こうした企業の生産性を確認する際に用いられているのが「生産性分析」です。
今回は、生産性分析の考え方や分析対象となる要素、具体的な計算方法について解説します。生産性分析を活用して企業活動を改善する方法にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
生産性分析とは資源からどれだけの成果を上げたのかをあらわす指標のこと
生産性とは、投入(インプット)した資源(ヒト・モノ・カネ・情報)によってどれだけの成果(アウトプット)を上げているのかをあらわす指標のことです。生産性分析とは、生産性を数値化して定量的に比較検討できるようにすることを指します。
生産性分析が注目・重視されている理由
なぜ近年になって生産性分析が注目・重視されるようになったのでしょうか。その大きな理由の 1 つに生産年齢人口の減少が挙げられます。
生産年齢人口とは、生産活動の中核を担う 15 ~ 64 歳の人口のことです。日本国内の生産年齢人口は1995年をピークに減少し続けており、現在のペースで減少していくと2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)まで落ち込むと推計されています。生産活動に従事する人が減っていく以上、 1 人あたりの生産量を増やしていかなければ産業全体の停滞を招くのは必然でしょう。生産性の低下を招いている原因を分析し、改善を図ることがあらゆる企業に求められているのです。
※内閣府「令和4年版高齢社会白書」
生産性分析を行う目的
生産性分析を行う主な目的は、客観的な数値に基づいて課題を抽出し、改善に役立てることです。
生産性分析を行うことによって、ヒト・モノ・カネ・情報が生産活動に効率良く活用されているかどうかを数値で把握できます。算出した数値を同業他社と比較したり、自社の前年度の実績と比較したりすることで、事業の実態を客観的に検証することも可能です。
生産性分析の結果をもとに現在抱えている課題を明らかにし、課題を解決していくことで経営改善につなげることが重要です。
生産性分析に欠かせない要素
生産性分析を行う際には、「インプット」「アウトプット」「付加価値」の 3 要素を用います。いずれも生産性分析に欠かせない要素のため、それぞれ何を指し示しているのかを押さえておくことが大切です。
インプット(投入量)
インプットとは、利益を上げるために投入した経営資源の量です。企業活動に必要なヒト・モノ・カネ・情報の総量がインプットにあたります。例えば、製造事業者であればモノを生産するために必要な工場や設備、原材料、部品、従業員、技術、資金などはすべてインプットに相当します。
アウトプット(産出量)
アウトプットとは、インプットによって創出された成果物の量です。製造事業者を例に挙げると、完成した製品はすべてアウトプットに相当します。より少ないインプットで多くのアウトプットを生み出すことを「生産性が高い」と表現します。
付加価値
付加価値とは、生産活動を通じて追加された新たな価値のことです。企業などが固有の努力や工夫によって生み出した価値が付加価値にあたります。例えば、仕入れた部品を独自の技術によって加工し、製品化した場合には技術が付加価値を生み出していると言えます。技術以外にも、独自のノウハウや仕入れルートなどによって生み出されたものは付加価値ととらえてよいでしょう。
付加価値の算出方法には「中小企業庁方式」と「日銀方式」の2種類があります。それぞれの計算方法は下記のとおりです。
一般的に多く用いられているのは、計算方法がシンプルな中小企業方式です。外部購入価値とは、材料費や買入部品費、外注加工費など他社から提供された価値のことをいいます。他社によってもたらされた価値を売上高から差し引くことで、自社が生み出した付加価値が算出できるという考え方です。
生産性分析の対象
生産性分析は、何をインプットととらえるかによって分析する対象が異なります。生産性分析でよく用いられる 3 つの要素について見ていきましょう。
インプットが「労働」の場合
インプットした経営資源を労働力と捉える場合、生産性は「労働生産性」と呼ばれます。労働生産性の計算式は次のとおりです。
労働者 1 人あたり、または労働 1 時間あたりに生み出された成果物の割合を示すのが労働生産性です。企業活動において単に「生産性」と言う場合、労働生産性のことをあらわしているケースが少なくありません。
インプットが「資本」の場合
インプットした経営資源を資本ととらえる場合、生産性は「資本生産性」と呼ばれます。土地や機械設備、社有車といった保有資本がどの程度利益に貢献しているのかを示すのが資本生産性です。資本生産性は以下の計算式で算出されます。
同じ土地や機械設備であっても、稼働率が上がればより多くの成果物を生み出すことができます。よって、資本生産性を向上させるには、稼働率や利用率を高める必要があると考えるのが一般的です。
インプットがすべての要素を含む場合
労働力や資本など、あらゆる要素をインプットととらえる場合の生産性は「全要素生産性」と呼ばれます。全要素生産性の計算方法にはさまざまなものがありますが、生産に必要な要素のなかには数値化が困難なものも含まれていることから、全要素生産性は増減であらわされます。
実際、従業員数や機械設備などの顕在化しているインプットに変化がないにもかかわらず、生産性が向上するケースは少なくありません。この場合、技術の進歩や作業効率の向上、新たなノウハウの習得など、可視化されていない要素が生産性向上に寄与した可能性が高いと考えられます。こうしたさまざまな要因を含めて生産性をとらえる場合には、全要素生産性が指標として用いられます。
生産性分析の活用方法
生産性分析によって、現状の生産性が数値化・可視化されます。こうして算出された結果をどのように活用すればよいのでしょうか。生産性分析の主な活用方法について解説します。
付加価値の向上
生産性分析は付加価値を向上させるために活用できます。
製品の生産量やサービスラインアップを短期間で大幅に増やすのは、現実的に難しいケースが多いでしょう。よって、製品やサービスの魅力をいかにして高め、顧客から選ばれるものにしていくかが問われます。このとき重要なポイントとなるのが「付加価値の向上」です。
生産性分析によって、現在、自社が創出している付加価値を数値化できます。その結果から、限られたリソースでより高い価値を生み出すためのノウハウを追求したり、新たなサービスを付加したりすることで、付加価値の向上を目指せるはずです。また、生産性分析を用いることで、付加価値向上の効果を可視化する際にも役立ちます。
従業員 1 人あたりの売上高の向上
生産性を分析することで、従業員 1 人当たりの売上高の向上につなげることもできます。生産年齢人口が今後も減少していくことを踏まえると、人材不足対策という意味でも有効な生産性分析の活用方法となるはずです。
労働生産性を継続的に分析していくことによって、従業員 1 人あたりの売上高がどのように推移しているかを客観的に確認できます。スキルの向上や作業効率の改善などにより、従業員 1 人あたりの生産量が高まれば、必然的に売上高や利益率も改善していくと考えられます。
従業員 1 人あたりの売上高を向上させることは、限られた人員で高い価値を生み出すために不可欠な要素と言えます。
資産の回転率の向上
生産性分析は資産の回転率向上にも活用できます。
資産の回転率とは、資産の活用が成果にどれだけ寄与したかをあらわす指標です。 1 年間のうちに総資産が売上に何回寄与したかを表す指標を総資産回転率といいます。例えば総資産回転率が 1 の場合、保有する資産を総動員して商品の生産や販売につながった回数が 1 回だけだったと判断できるのです。
資産の回転率が高いほど、現状の設備などを生産活動に効率よくつなげられている状態といえます。生産性分析を通して、現状の資産活用がどのくらい効率的なのか、改善の余地があるかどうかを判断するヒントになるはずです。
生産性を分析して経営改善に役立てよう
生産性分析は、インプットした資源がどれだけの成果をもたらしているかを測るための手法です。少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少していくことがほぼ確実となった今、生産性分析を通して経営改善を図ることはあらゆる企業に求められている試みといえるのではないでしょうか。
今回紹介した分析・活用方法を参考に、ぜひ生産性分析に取り組んでください。自社の課題を客観的に分析し、改善を図っていくことで、長期にわたって安定した経営基盤を築けるはずです。
よくある質問
HOME > Slack 日本語ブログTOP >生産性> 生産性分析とは?対象となる生産性と計算式、活用法について解説