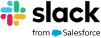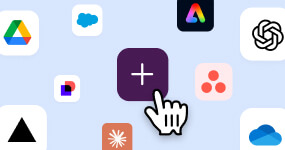日本の労働生産性が諸外国と比べて高いのか低いのかが、気になったことはありませんか?働き方改革が掲げられるなか、本当に労働生産性を高める必要があるのか、国際的に見て後れを取っているのかといったことを知らないと、あまり実感がわかないという人もいるでしょう。
今回は、日本の労働生産性が本当に低いとすれば、その理由がどこにあるのかを解説します。また、労働生産性の低さが引き起こす弊害や、労働生産性を高める方法にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
日本の労働生産性は低い
結論としては、日本の労働生産性は国際的な水準と比較して低いのが実情です。2023 年時点で日本の労働生産性はどのような位置づけになっているのかを、業種別の労働生産性で見ていきましょう。
OECD 加盟国 38 ヵ国中 27 位
公益財団法人日本生産性本部が発表した「労働生産性の国際比較 2022」によると、OECD(経済協力開発機構)のデータで日本の時間当たりの労働生産性は 49.9 ドルと、OECD 加盟 38 ヵ国中 27 位、主要 7 ヵ国で最下位という結果です。国際的な水準でとらえた場合、日本の労働生産性は低いと言わざるをえません。
また、27 位という結果は 1970 年以降最も低い順位となっています。これは、日本の労働生産性は諸外国と比べて伸びが鈍いことや、主要 7 ヵ国以外の国々にも追い抜かれつつあることを示しているのです。
※公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較2022」
業種別に見る労働生産性
労働生産性は業種によって差があることも、押さえておくべきポイントと言えるでしょう。労働生産性の高い業種・低い業種は次のとおりです。
※公益財団法人日本生産性本部「主要産業の労働生産性水準の推移」
資本集約的な業種は労働生産性が高い一方で、人手を必要とする業種では労働生産性が低くなりやすい傾向があります。また、2000 年には OECD 加盟国のなかで労働生産性がトップだった製造業に関しても、2022 年時点では 35 ヵ国中 1 8位まで後退している状況です。
労働生産性とは?
そもそも「労働生産性」とは、何をあらわしている指標なのでしょう。労働生産性とは、投入した資源(インプット)に対してどれだけの成果(アウトプット)が得られたかを示す指標です。労働生産性の考え方をより正確に理解するには、計算方法と種類を理解する必要があります。
労働生産性の計算式
労働生産性は、投入した労働力に対する成果の割合であらわされます。労働生産性を求める計算式は以下のとおりです。
つまり、投入する労働量が少ない状態で高い成果を上げれば、労働生産性が高まることがわかります。これは、従業員の時間当たりにこなせる作業量が増えたり、より少人数でアウトプットが行われたりすることが要因です。
労働生産性の種類
労働生産性には、大きく分けて「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」の 2 種類があります。
物的労働生産性とは「生産量や販売金額といった成果物や金額」にあらわれる生産性のことです。投入した労働量に対して、より多くの生産量や売上高を確保することで、物的労働生産性は上がります。
一方、付加価値労働生産性とは「生産活動を通して新たに生み出した価値」としてあらわれる生産性のことです。例えば、仕入れた原材料を加工して販売した場合、売上高から原価を差し引いた「粗利」が生まれます。付加価値労働生産性は、このようにとらえるとわかりやすいでしょう。
日本の労働生産性が低い理由
なぜ日本の労働生産性は国際社会のなかでも低い水準にとどまっているのでしょう。主な理由として、次の 4 点が考えられます。
付加価値を生み出す力が弱い
労働生産性が低迷している大きな理由のひとつは、付加価値を生み出す力が弱いことです。ひとつの業務に携わる人数が多くなったり、作業する時間が増えたりすれば、付加価値は低くなってしまいます。アメリカやドイツといった工業先進国と比べると、同じ価値を生み出すために日本で投入されている労働者数や労働時間は多いため、付加価値を生み出す力が弱く、結果として労働生産性が低くなっています。
長時間労働という手法
日本の労働生産性が低い理由には、「長時間働き続ける人は勤勉」といった風潮が根強く残っていることが挙げられます。近年では働き方改革の推進により残業時間の上限規制が設けられましたが、残業が前提の働き方をしている職場が多く残されているのが実情です。
従業員の集中力は、労働時間が長くなれば低下し、判断ミスや操作ミスを誘発します。結果的に時間当たりの作業量が低下したり、人的ミスによる作業の手戻りが頻発したりしやすい状況を作っているのです。
評価制度が適切ではない
評価制度が適切でないことも、日本の労働生産性を低下させている一因と言えるでしょう。日本企業には年功序列の給与体系が根強く残っており、成果主義に基づく評価制度を採用している企業は少ないのが実情です。例えば勤続年数に応じて自動的に昇給していく仕組みになっていたり、労働時間が長いほど残業手当を多く受け取れる給与体系になっていたり、成果による評価でなかったりする側面があります。
こうした評価制度は「頑張らなくても評価は変わらない」といった認識を従業員にもたらし、モチベーションの低下を招きます。
個人の裁量が小さい
役職者に決裁権が集中しており、従業員個人の裁量が限られていることも労働生産性を低下させている一因です。「上長の判断を仰がなければ業務を進められない」「形式的な社内文書で公表されるまで実作業に取りかかれない」といったケースが多ければ、必然的に仕事を進めるスピードは落ちます。
また、チームで仕事を進めることが前提になっている場合、仕事が遅いメンバーのフォローに回されるため、本来の業務に集中できない状況が生まれがちです。個人の裁量で仕事を進めにくいことは、日本の労働生産性低下を招いている原因と言えます。
労働生産性の低さが引き起こす弊害
労働生産性の低い状況が続くことによって、企業にとってどのようなデメリットをもたらすのでしょうか。労働生産性の低下が引き起こす主な弊害について解説します。
賃金コストの増加
労働生産性が低ければ、ひとつの仕事を完了させるために長い時間が必要になります。労働時間が増加すれば支給すべき残業手当も増えるため、結果として賃金コストの増加を招く原因となるのです。また、長時間労働の常態化は従業員の集中力やモチベーションの低下を招き、業務の質が低下することもあるでしょう。時間当たりに生み出す付加価値が下がることは、相対的な賃金コスト増に拍車をかける原因なのです。
従業員への負荷の増加
生産性の低い仕事の進め方から脱却できない状態が続くと、従業員一人にかかる負荷が増していきます。過度な残業や休日出勤などが増えれば従業員は疲弊し、業務に対するモチベーションを低下させ、労働生産性がさらに下がる悪循環に陥りかねません。つまり、労働生産性が低い状態が続くことは、従業員一人ひとりの心身に悪影響を与えるばかりか、組織全体の活力が失われる要因にもなるのです。
経済力の低下
労働生産性の低迷は企業全体の経済力を低下させ、事業の存続を危うくするリスクになるでしょう。付加価値を生み出す力が弱いということは、企業として「稼ぐ力」が弱いことを意味しています。労働時間に対して十分な成果を上げることができなければ、売上も低迷してしまうでしょう。さらに、売上を増やすためにコストも増加させれば、利益が圧迫される原因にもなります。
日本の労働生産性を高める方法
では、日本の労働生産性を高めるには、具体的にどのような施策を講じていけばよいのでしょうか。特に重要度の高い 5 つの施策を紹介します。
評価制度の見直し
日本の労働生産性を高めるには、賃金計算の基準が労働時間にならないよう、評価制度の見直しが必要なケースもあります。長時間働いた従業員ほど多くの給与を得られる仕組みになっている限り、長時間労働を是正していくのは現実的に難しいからです。個人の工夫や業務プロセスの改善によって成果を上げる従業員が評価されるよう、評価制度を見直していく必要があります。
さらに、成果に応じてインセンティブを支給したり、労働生産性に関する評価軸を追加したりすることで、社内の意識改革を図っていくことも大切です。
DX 化の推進
DX 化の推進も労働生産性の向上に欠かせない方法です。IT ツールを導入・活用することにより、情報共有の精度・速度の改善や定型業務の自動化につながります。
例えば、ビジネスチャットとしても人気の Slack のようなコミュニケーションプラットフォームを活用するのも有効です。メールや電話、対面に限られていた従来のコミュニケーションを、グループチャットやハドルミーティング、ビデオ会議などに置き換えることで、状況に応じて適切なやり取りを選択しやすくなります。上長による決裁や業務指示も Slack 上で完結できるため、業務が中断されるような状況が発生しにくくなります。
付加価値の見直し
業務を通じて生み出す付加価値そのものを見直し、成果に対する利益を高めていくことも、日本の労働生産性を高めるために重要なポイントです。例えば、現状の価格設定が商品やサービスに見合ったものになっているか、安く売ることが前提になっていないか改めて見直してみてください。
自社の付加価値を過小評価しないことは、価格競争に巻き込まれるリスクを低減させるためにも重要な視点と言えます。しかし、商品・サービスの単価を上げる際には、サービスの充実化を図るなど顧客に納得してもらえる形を目指すことが大切です。
個々のスキルの尊重
日本の労働生産性を高めるためは、従業員の個々のスキルを尊重することも視野に入れるといいでしょう。例えば、現状チーム単位で業務を進めているようなら、個人単位で仕事を進めやすい体制に変えていくのも効果的です。優れたパフォーマンスを発揮している従業員が、仕事の遅いメンバーのフォローに回らなくて済むよう、各自がこなすべき業務を明確化するのもいいかもしれません。
個々のスキルを尊重する仕事の進め方が定着することで、誰がどれだけの仕事量をこなしているのかが明確になり、より公平な評価をしやすくなるという点も大きなメリットです。
アウトソーシングの活用
労働生産性を高めるために、すべての業務を社内で完結させる必要はありません。必要に応じてアウトソーシングを活用することもできます。例えば、業務を外注すれば、従業員の人材育成に費やす時間を削減できるでしょう。
業務を外注する場合、自社の業務を利益につながる業務(コア業務)とそれ以外の周辺業務(ノンコア業務)に分け、ノンコア業務をアウトソーシングしましょう。周辺業務が削減されることにより、従業員は本来取り組むべき業務に集中しやすくなるので、労働生産性が高まります。
労働生産性の向上施策を行い従業員にポジティブな効果をもたらそう
日本の労働生産性は、国際的な水準と比較して低い実情があります。今後、生産年齢人口が減っていくことを視野に入れれば、労働生産性の向上施策は早急に取り組むべき課題と言えるでしょう。
今回紹介したポイントを参考に、ぜひ労働生産性の向上を実現するための取り組みを検討してみてください。労働生産性が高まることで業績が改善するだけでなく、従業員のモチベーションアップや定着率の改善など、ポジティブな効果がもたらされていくはずです。
よくある質問
HOME > Slack 日本語ブログTOP >生産性> 日本の労働生産性は低い?その理由と改善に向けた施策を解説