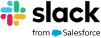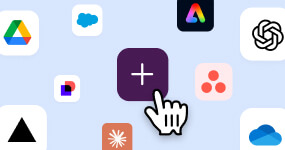業務プロセスの改善は、業務効率化や生産性向上を実現する上で欠かせない視点です。働き方改革の推進が求められている昨今、労働時間を削減する手段としても有用でしょう。
今回は、業務プロセスを改善するメリットや改善に失敗する理由、成功させるためのポイントをわかりやすく解説します。業務プロセス改善に利用できる IT 技術や具体的な改善の手順も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
業務プロセスとは、目的達成に必要な行動のこと
業務プロセスとは、目的達成のために必要な行動のことです。企業は部門や部署によって区分されており、それぞれのセクションごとに役割が与えられ、担当者に作業が割り振られているのが一般的です。
ですが、従業員は各自が思うままに仕事を進めているわけではなく、一定のルールや手順に従って作業し、組織全体の目的を達成していきます。このとき、目的達成のために必要とされる行動が業務プロセスなのです。
例えば、製品を製造して販売する場合の業務プロセスは、一般的に下記のような行動になります。
業務プロセスと業務フローの違い
業務フローは業務の「流れ」を表す言葉です。作業を開始してから完了するまでの間に、どのような手順で何をすべきかを示す流れが「業務フロー」であり、最終的な目的達成のために多くの業務フローが組み合わされたものが「業務プロセス」といえます。
業務プロセスの改善で業務の 3M を解消
業務プロセス改善とは、事業活動の最適化や効率化、コストダウンなどの目的を達成するために業務プロセスを見直し、より良い形にしていくことを指します。
組織が投じられるリソースは有限であることから、できるだけ無駄や偏りのないよう、適切にリソースを配分することが重要です。特に、業務の 3M と呼ばれる「ムリ・ムダ・ムラ」を解消することが、業務プロセス改善につながります。
業務プロセス改善と働き方改革の関連性
業務プロセス改善と働き方改革には深い関わりがあります。働き方改革を推進するには、長時間労働の是正や休暇のとりやすさなど、労働環境の改善に向けた取り組みが欠かせません。ですが、単に働く時間を減らすだけでは業務量が減少し、生産性が落ちてしまいます。
そこで必要とされるのが、業務効率化や生産性向上です。ですが、業務効率化や生産性向上は、担当者や部門単位で業務フローを改善しても組織全体の業務プロセスが従来どおりであれば、改善するのは困難です。
そこで、働き方改革を推進しながら業務効率化や生産性向上を行うには、業務プロセス全体の改善が欠かせません。
業務プロセス改善のメリット
業務プロセス改善によって得られるメリットには、「業務効率化・生産性の向上」「IT や DX の促進」「リスクマネジメント」「業務の属人化防止」があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
業務効率化・生産性の向上
業務プロセス改善によって、業務効率化や生産性向上のメリットがあります。例えば、営業担当者が記入した紙の注文書をもとに経理担当者が売上データを入力していく場合、「注文書を作成する」「売上データを入力する」という作業で遅延が発生する可能性があります。
ですが、注文データをシステムで一元管理し、営業担当者が入力したデータがリアルタイムで反映されれば、経理担当者が再度入力する作業は不要となります。また、入力ミスや集計ミスも防げることから、組織全体での業務効率化や生産性向上を実現可能です。
IT化 や DX の推進
業務プロセス改善は、 IT 化や DX を推進促進していくための下準備になります。これは、IT 化 や DX でデジタルツールを導入し活用することで、業務の効率化や生産性の向上、働き方の抜本的な改革を達成することができるからです。
リスクマネジメント
業務プロセス改善は、リスクマネジメントにも寄与します。リスクマネジメントの基本は、組織内に潜むリスクを発見し、分析・評価して対処していくことです。業務プロセスが不透明であれば、そもそも「リスクがないといえる状態」の基準がなくなります。業務プロセスを整理し、組織内で統一された標準的な行動が定まれば、リスクマネジメントもできるのです。
業務の属人化防止
業務プロセスの改善は、業務の属人化を防止する策としても有効です。業務プロセスが従業員に属人化している場合、特定の従業員が欠勤したり退職してしまったりすると、ほかの従業員では業務を進められなくなるかもしれません。結果として顧客の信頼を失ったり、取引先との間でトラブルの原因となったりすることも想定されます。
業務プロセス改善を通じて標準化を推進することは、業務の属人化・ブラックボックス化を防ぐためにも必要な取り組みです。
業務プロセス改善が失敗する原因
業務プロセスの改善を行っても、効果があったのかどうかわからないケースがあります。これは、業務プロセス改善の評価や目標が決まっていないと発生することが多いです。
また、業務プロセス改善を望まない従業員による、抵抗が発生するケースもあります。ここでは、業務プロセス改善が失敗する原因をご紹介しましょう。
効果測定や客観的な評価をしない
業務プロセス改善の計画を実行したとしても、効果測定や客観的な評価をしなければ成功率は著しく下がります。業務プロセス改善に取り組んだことによって、どのような結果が出たのか、何がどう改善されたのかを測る指標がないため、「なんとなく良くなった」といった感覚的な評価に終始することがあります。
事前に、何をもって業務プロセス改善の「成功」とするのかを定義した上で、効果測定を実施して PDCA サイクルを回していくことが大切です。
曖昧な目標
目標が曖昧なまま業務プロセス改善を進めてしまうことも、失敗の大きな原因のひとつです。例えば、「仕事をしやすい業務プロセスに変革する」という目標を掲げた場合、具体的に何をどのように改善するのか、どうなれば目標を達成できるのかがわかりません。
変化を望まない従業員
業務プロセス改善にはメリットがありますが、いざ推進が現実になると現場の反発を招くこともあります。それは、従業員の中には、現状を大きく変えることに抵抗を感じる人がいるからです。
実際、業務プロセス改善によって従来の業務のやり方が変わったり、一時的に負担が増したりすることは十分に考えられます。ですから、まずは業務プロセス改善に取り組む目的や、中長期的に見た場合のメリットについて現場の理解を促していくことが大切です。
業務プロセス改善を成功させるためのポイント
続いては、業務プロセス改善を成功させるために押さえておきたいポイントを紹介します。業務プロセス改善の効果を十分に引き出すには、下記のようなポイントを実践していくことが大切です。
改善の理由や根拠を明確にする
なぜ現状の業務プロセスにメスを入れる必要があるのか、具体的な理由や根拠を明確にしておく必要があります。業務プロセスには複数の部門が関わっているケースが多いことから、「今までどおりのやり方に問題を感じていない」「かえって負担が増えるなら協力したくない」といった受け止め方をする従業員が出てくる可能性があるからです。
現状の業務プロセスに潜む課題を可視化し、改善結果を具体的な数値で示すことによって、業務プロセスに取り組む必要性を実感してもらうことが大切です。
PDCA を意識する
業務プロセス改善は、一過性の取り組みではありません。PDCA を意識し、実行と改善を繰り返して効果を高めていくことが求められます。
それには、現状の課題を示す数値に対して、改善後に目指すべき数値を掲げます。あるべき姿と現状とのギャップを埋めるための施策を講じ、効果を検証した上で再び施策へと反映させていくことが大切です。この PDCA サイクルを繰り返すことにより、業務プロセス改善の効果が着実に高まっていきます。
DX の推進や働き方改革も行う
業務プロセス改善は単体で推進するのではなく、DX の推進や働き方改革も並行して進めていくことが重要です。DX の推進や働き方改革をする場合、局所的にツールを導入したり、業務フローを改善したりするだけでは成功しません。
業務プロセスを見直すことと、改善に必要なツールを導入すること、結果として働き方改革が実現することは、業務プロセス改善につながるのです。
現場のヒアリングする
現場のヒアリングを実施し、実際に業務に携わっている各担当者の考えを把握しておくことも重要なポイントです。業務プロセス改善は、経営層や特定のプロジェクトチームが推進すれば成功するものではありません。業務プロセス改善を有意義なものにするためには、現場の従業員が感じている課題点や問題点を解決するスタンスで臨むことが大切です。
継続的に見直しを実施
業務プロセスの改善は、改善策を講じること自体がゴールではありません。実際にどの程度の効果があったのか効果測定を実施し、必要に応じて調整や見直が必要です。ある時点で最適解だった業務プロセスが、時間の経過とともに業務実態と合わなくなっていく可能性もあります。効果の検証と見直しを繰り返し、継続的に改善を図ることが求められるのです。
コンサルティングに依頼する
業務プロセス改善を効果的に進めるには、外部のコンサルティングに依頼するのも有効です。自社の従業員や役員が、慣れ親しんできた業務プロセスの課題や問題点を客観的に分析するのは容易ではありません。実績が豊富なコンサルティング会社に相談することによって、改善が必要なポイントを指摘してもらいましょう。
業務プロセス改善に利用できる IT 技術
続いては、業務プロセス改善に役立つ IT 技術の例をご紹介します。IT 技術ありきで改善策を検討するのではなく、あくまでも手段のひとつと捉えることが重要です。業務プロセスの改善に利用できる IT 技術としては、下記のようなものが挙げられます。
OCR
OCR(光学的文字認識)は、紙に印刷された文字や手書きの文字を読み取り、デジタルのテキストデータに変換する技術です。業務プロセスで紙の書類をやりとりするシーンが多い場合に効果を発揮します。手で入力していた時間が削減されるだけでなく、誤入力などの人的ミスの抑制にも効果的です。
FAX の電子化と基幹システムとの連携
業務プロセスに FAX の利用が含まれているようなら、FAX の電子化と基幹システムとの連携が有効です。届いた FAX の内容をデータとして手入力する手間が削減されるだけでなく、基幹システムへ直接反映させる仕組みにすることで、FAX の受信からシステムに反映されるまでのタイムラグをなくせます。
事業のオンライン化やペーパーレス化
オンライン上で受発注業務を完結させるなど、事業をオンライン化していくことも業務プロセス改善に寄与します。従来は紙の伝票でやりとりしていた情報をデータに置き換えれば、ペーパーレス化も同時に実現可能です。
アウトソーシングの活用
定型業務をアウトソーシングすることも、広義の意味で IT 技術の活用といえます。例えば、伝票入力のような単純作業を外注することで、自社側では入力後のデジタルデータを起点に業務を進められるからです。
AI や RPA、BPO による業務の自動化
AI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用して、業務を自動化するのも業務プロセス改善に効果的な方法です。例えば、AI チャットボットを導入することで、基本的な問い合わせへの応答に、有人オペレーターは必要ありません。また、定型業務の中には、RPA で自動化できるものもあります。
ほかにも、業務プロセスの一部または全体を BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)によって外注化することで、業務の自動化とプロセス改善を両立できます。単純なアウトソーシングとは異なり、業務プロセスの改善も視野に入れて外部委託できる BPO を活用しましょう。
ビッグデータを活用
自社が保有するビッグデータを有効活用することも、業務プロセス改善に役立つ場合があります。社内に蓄積されていた膨大なデータから、購買履歴や顧客の属性データなど、新たな傾向や特徴が見つかることも珍しくありません。
テレワーク
事業のオンライン化やペーパーレス化を推進することによって、テレワークへの移行が可能です。就業場所を選ばない働き方ができるようになれば、居住地を問わず優秀な人材を採用することも可能になり、業務プロセスを改善しやすくなります。
また、通勤時間が削減されれば、従業員がプライベートの時間をより多く確保できますので、働き方改革やワークライフバランスの改善にも効果的です。
クラウドストレージを活用
クラウドストレージの活用によってデータを一元管理できることに加え、共同編集の機能も活用できます。従来はファイルをやりとりしていたプロセスをクラウドストレージ上で完結できるため、業務プロセスをシンプルにできる点がメリットです。
また、自社サーバーでデータを管理する場合と比べて、BCP(事業継続計画)への対策を講じやすいという長所もあります。
業務プロセス改善の手順
次に、業務プロセス改善を進める際の手順を解説します。表層的な業務効率化や業務改善にとどまらないようにするためにも、下記の順序で改善策を講じていくことが大切です。
1. 業務を可視化
まずは現状の業務の可視化です。既存の業務プロセスがどうなっているのかを正確に把握していなければ、業務プロセスが抱えている課題の抽出もできません。現場へのヒアリングをもとに、業務プロセスを図式化しておく必要があります。
2. 改善する課題の整理と方針の策定
可視化された業務プロセスのうち、改善が必要な箇所を特定します。初めから大きな改善ポイントを探すのではなく、大小を問わずすべての課題を列挙してから、優先順位をつけていくのがポイントです。優先順位の高い課題について、「手順の変更」「IT ツール導入」「部門の統合」といった対策を策定していきます。
3. 実行計画の策定
業務プロセス改善の対策方針に沿って、具体的な実行計画を策定します。実行計画には「いつまでに・誰が・何を・どこまで・どのように」実行するのかを盛り込むとともに、KPI を設定しておくことが大切です。目標を設定して取り組むことで、目標に対しての進捗がどの程度であるかが確認しやすくなります。
4. 計画を実行
計画の策定が完了したら、実行しましょう。業務プロセスの改善は、短期間で成果が出るとは限りません。策定した計画のうち、効果が出やすいと思われる改善策や小規模で実行可能な改善策から実行していくことで、効果を実感できます。改善の規模を徐々に大きくしていき、最終的に組織内の業務プロセス全体の最適化を目指しましょう。
5. 結果の振り返り
改善策の実行後は、必ず効果の測定と検証を行い、業務プロセス改善がどの程度図られたのか結果を振り返ることが重要です。改善後の状況と目標との差異を確認したうえで改善を繰り返し、業務プロセスをブラッシュアップしてください。
業務プロセス改善に Slack を活用する方法
業務プロセス改善には、インテリジェント プロダクティビティプラットフォームの Slack を活用できます。例えば、Slack canvas に共用データを集約することにより、場所を選ばず必要な情報にいつでもアクセス可能です。また、従来はメールや口頭で伝えてきたノウハウやナレッジをcanvas に集約して、検索するだけで素早く確認できるようにします。
Slack にはワークフロー機能が備わっているため、ワークフローから canvas を作成・更新をしたり、リアルタイムでデータを取り込んだりすることも可能です。さまざまな業務を自動化することで、業務プロセスの標準化をサポートします。
業務プロセス改善を、組織の課題解決につなげよう
業務プロセスの改善は、局所的な業務フローの改善や業務の効率化ではなく、事業の目的達成に必要な一連の行動にメスを入れることを指します。そのため、業務プロセス改善に取り組む意義やメリットを十分に把握しておかなければ、表層的な改善に終始してしまったり、現場から反発を買ったりする結果にもなりかねません。
今回ご紹介したポイントや手順を踏まえて、業務プロセス改善を組織の課題解決につなげていくことが大切です。
よくある質問
HOME > Slack 日本語ブログTOP > 変革 > 業務プロセスの改善はどう行う?メリットや成功させるポイントを解説